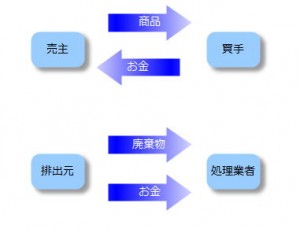新年度も始まりましたが、相変わらずバタバタと落ち着きの無い日々を過ごしています。当社の決算は12月なので、数年前までは年度末と言っても関係なかったのですが、最近は補助事業をいくつか取り組んでいますので年度末、年度初めの書類作成が多く追われる日々です。
そんな中で、当社では販売管理システムを導入することを検討しており、システム導入の費用に充当すべく補助事業の書類を作成しています。最近、業務拡大に伴いお客さまとの取引件数が増加してきており、どうにもこうにも手が回らなくなってきたので業務効率の向上をはかるためにシステム導入を検討している次第です。手書き伝票とFAXで処理することの限界を感ている今日この頃です。
零細企業である当社が販売管理システムを導入するのは大きな投資ですが、顧客情報の集約化により業務効率の向上だけではなく、データ分析により次の仕事への展開を図っていきたいと思っています。これからの時代はシステムをいかにうまく使いこなしていくかが求められています。
最近、当社のお客さまである農家でもシステム導入が徐々に進んでいます。たとえば、稲作オペレータ向けのクラウドシステムでは、圃場とGPS位置データをひもづけし、それぞれの圃場での作業履歴、収量データなどを蓄積できるような仕組みがとられています。それぞれの田んぼでどんな作業をし、どれぐらい収穫したかを記録することでそれぞれの田んぼの成績がきちんと把握できるようになるわけです。いわゆる「見える化」というやつです。作業効率が悪い圃場、収量が劣っている圃場(さらには作業効率が悪いスタッフ)がどこなのかが一目瞭然になるということです。

事業の改善には現状の成績を正確に把握することが非常に重要です。現在の成績把握がその次の「カイゼン」につながります。自社内での比較、さらには他社との比較をすることで今の立ち位置が明確になるわけです。
同様のシステムは畜産農家向けのものもあります。畜産農家も個体の成績を把握することで、成績改善、事業収支の向上につなげることができます。たとえば、豚屋さんでは母豚あたりの離乳頭数、離乳体重、出荷日齢、日増体量、投薬履歴、飼料給与量といった項目を管理することが求められており、これらの管理項目をクラウドを利用してデータを蓄積すると言ったことが行われています。
ただ、システムは非常に大きな武器ではありますが、所詮は道具であり手段に過ぎません。本当に成績がよい農家は紙ベース、Excelベースでもデータをきちんと残す習慣があり、データから分析を行なう事を実践しています。Excelでも使いこなしようでは強力なデータベースとして利用することができ、当社のお客さまでもExcelに過去のデータをすべて入力して、成績の推移を把握されている方がみえます。
逆に言うと、今まで記録するという習慣が無い人がシステムを入れたからすぐに記録するようになるかは怪しいところです。記録する習慣が無ければ、いくらシステム導入しても結局は記録を残すことは無く終わってしまいます。(昔からの真の職人気質の方は記録すること無くあらゆるデータを記憶されていることがありますが・・・。)システムは便利な道具ではありますが、目的では無いことを念頭に置くことが重要です。また、単に記録するだけでは無く、それを比較分析する能力も必要となります。
これは、農業だけでは無く、あらゆる分野においても言えることかと思います。データ記録する習慣を確立し、いかに記録を活用していくかがこの激動する社会情勢で生き残っていくために求められています。当社も自社の立ち位置を把握し、次への戦略を打ち出すことができる企業になれるように努力していきたいと思います。