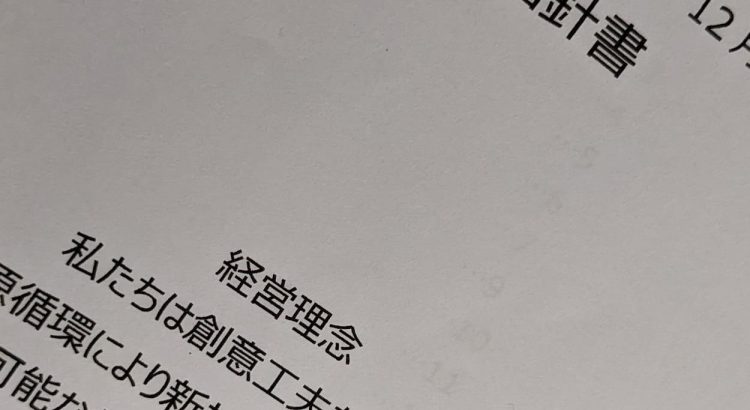年度末の超多忙期が過ぎましたが、最近は新聞連載や雑誌寄稿、講演依頼などが多く忙しくしています。原稿を書くのは良いのですが、締め切りに追われ余裕がない状態が続いています。その割に釣りにだけは行っていますが(笑)

出張が多いのも忙しい理由の一つで、先日は出張で麻布大学で行われた養豚学会に参加しました。当社は畜産関係の学会にいくつか参加しており、養豚学会にはよく出席していて研究機関の先生とかなりお知り合いになりました。養豚学会は小規模な学会のため、参加メンバーも多くありません。参加者は研究機関の研究者が中心で、配合飼料メーカーや動物医薬品の参加はありますが、生産者や当社のようなエコフィード製造業はほぼ参加していません。生産者からすると学会に参加するというのはハードルが高いと思いますが、これは非常にもったいないことだと思います。
学会に参加していて感じるのは、研究の内容以前の問題として研究課題設定がおかしいケースがよくあるということです。実用化するのにはあまりにコストがかかりすぎて現実的ではない試験テーマであったり、生産者から見るとニーズがない分野であることがその原因です。また、最近の生産現場のトレンドの移り変わりは激しく、試験設定自体が時代遅れになっていることもあります。これらの問題が発生するのは研究機関の方が実際の生産者と膝を交えて話をしたり現場に赴く機会が少ないことがその一因ではないかと思います。
生産者が学会に参加しないのは「どうせ研究者のやることは現場に役に立たない」と思っている部分もあるかと思います。お互いに交流が無いことで悪循環になっているように感じます。
当社は学会に参加するだけでなく、多くの大学と共同研究を行っています。共同研究先でお願いする研究テーマは当然ながら現場に即したものをですが、それだけではなく、学術的に新規性があり、学会発表をしやすいものをご提案しています。当社は新規の飼料の引き合いが多く、使用実績が無いものもたくさんあります。そういった新しいアイテムを現場に落とすため、大学での研究は非常に役立っています。

研究機関の人はもっと現場に出るべきだと思いますし、生産者ももっと研究機関を活用することで、よりよい生産が可能になります。産学官連携推進がうたわれていますが、まずは現場での交流がスタートになるかと思います。当社もそういった取り組みのお手伝いをすることで、業界の発展にすこしでも貢献できたらと思います。